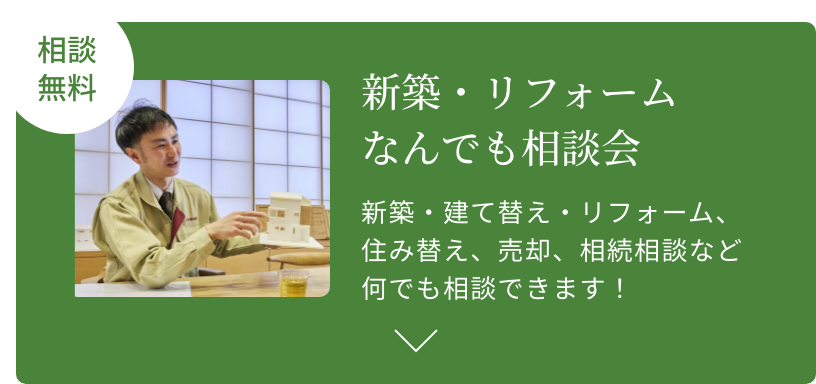日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
北風がびゅーびゅー音を立てています。家の中にいても分かるのでかなりの強さ・・・寒そうです・・・いや寒い!外に出たくない感じです・・・そうも言ってられません。
今日は成田東の内覧会があるので・・・天気は快晴ですが・・・ということで、今日は仕事です。
これから出かける準備をしますので、本題は次の機会に・・・ご容赦ください。
寒い日曜日になりますが、内覧会やってます。成田東モデルハウスと花小金井の同時開催です。詳しくは弊社HPのイベント情報をご覧ください。
寒さにめげず、開催しています。
今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
快晴の朝、冷え込みました!これはもう冬の朝ですね。今朝は久しぶりに時間がありますので3週間ぶりに本題へと参ります。
中山法華経寺祖師堂の話の続きとなります。3週間前覚えておりますか?妻が二つ並んでいる面白い屋根の形をしたお堂です。「比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)」と言います。お寺のお堂でこの屋根はここだけ、神社では岡山県吉備津神社の国宝建造物の社殿がありますが、印象が違うような気がします。
この祖師堂、江戸時代中期延宝6年(1678年)に建立された大きな7間堂です。(7間という意味は柱間が7つあるという意味で寸法単位の間ではありませんので)
昭和62年から10年かけて平成10年に創建当時の姿に戻しこの比翼入母屋の屋根になりました。それまでの屋根の形は3週間前の「日曜の朝に」掲載しましたが、どちらが良いか?となると無理に創建当時にしなくてもと思ってしまうのは私だけではないはず。今の屋根見るからに雨仕舞が悪そうです(下の写真をみても・・・どうでしょうか)。
平面の大きさにしては高さが少ないのではとも・・・高い方が宗教建築として威厳が出るのではと・・・だから昔の人は改修して大きな屋根を架けてしまったのでは・・・といろいろ考えさせてくれる中山法華経寺祖師堂なのです。

中山法華経寺祖師堂の屋根
平面の割に低いような気するのは私だけ?
それでは失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
快晴の朝です!気持ちのいい青空!風はつめたいが・・・先週に日曜日とは打って変わっての良い天気に日曜日。一昨日の文化の日からよい天気続いています。10月の休みは良い天気がなっかたので待ちに待っていた方も多いのでは・・・出かけちゃってますか~
という私これから成田東のモデルハウス内覧会の担当ということで10時から4時までそこにいます。お仕事です。散歩がてらにお立ち寄りください。また同時開催で「花小金井のきれいな空気の家」完成内覧会も行なっています。お待ちしております。(くわしくはHPイベントご覧ください。)
と言うことでこのブログも会社で書いている次第で・・・これからモデルハウスに行きますので、今日も本題は控えさせていただきます。ご容赦願います。
では今日はこの辺で失礼いたします。良い日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
とは言うものの日曜日はあと1時間となった夜なので・・・改めてこんばんは・・・と
今日は会社のホームオーナ様とのイベントで早朝から出かけ1日中留守でしたので、この時間になりました、ご容赦願います。
こんな時間です・・・今朝は早かった・・・眠いです・・・・・・・
ということで今日はこの辺で失礼いたします。簡単ですがお許し願います。
今週も良い日々が続くように・・・
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
激しく降っています・・・言うまでもないですが・・・選挙に行かないと・・・明日までは辛抱の天気です、災害・事故など何事も起こらなければよいのですが・・・
先週、予告をしてしまったので本題に参りましょう。千葉県編の第3段、珍しいお堂といくつかの国指定重要文化財建造物があるところ・・・ありました。
市川市の中山法華経寺です。日蓮宗の大本山、中山競馬場の南西1㎞に位置している名刹です。4棟の国指定重要文化財建造物があります。
その中でまずらしいお堂が「祖師堂」になります。お祖師様=日蓮上人をお祀りしているお堂で他の宗派でいうと本堂にあたる建物になります。よって法華経寺の国指定重要文化財建造物のなかで一番大きい建物となります。まずはこの姿をご覧下さい。

中山法華経寺祖師堂
いかがでしょうか?どこにもない形「比翼入母屋造り」と言います。屋根が並んでくっついています。雨の処理が心配になる屋根です。
江戸時代中期延宝6年(1678)建立の建物になります。この屋根の形、以前は違っていました、解体修理をした際に創建当時の屋根の形=比翼入母屋造りになりました。それでは修理前の屋根をご覧ください。

改修前の法華経寺祖師堂
いかがでしょうか?どちらがいいのか迷いますが、その話は次回に・・・・
それでは今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
雨の日曜日です。寒いですね~体調崩していませんか?最近の温度差は調子が狂います・・・きょうは何をしようか・・・と
本題と参りますか・・・
千葉県編を始めまして2カ所を巡ってきました。珍しいお堂の笠森寺観音堂に触れました・・・あっ!まだ千葉県には珍しいお堂がありました!
次はそこを訪ねてみましょう。そのお堂は解体修理をして創建当時の姿に戻され、他にない姿のお堂になったのです。修理前の写真を現在探していますので次回にはっきりと・・・今日は予告編にさせていただきます。
ということでこの辺で失礼します。(手抜きでごめんなさい)よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
今朝はまぶしい日差しがさっきはあったのですが・・・空には薄雲が、昨日出来なかった運動会が振替になり各地で開催されているのではないでしょうか、今日は温度が上がり暑くなるとのこと、寒暖差により体調お気遣いください。
今日も時間がありますので、本題へ、先週の続きと参りましょう。千葉県長南町の笠森寺観音堂のお話を・・・
「四方懸造り」という他にない造りをしている珍しいお堂なのです。いわゆる山の(岩と言っても良いか)頂きの上にお堂を建築したので四方の床が高くなったということ、江戸時代の名所絵図をご覧ください、かなり誇張していますが山頂に立っているということがわかるかと思います。

笠森寺観音堂
江戸時代の名所絵図
山の頂に観音様をお祭りし、お堂をつくったというのが、この観音堂です。このような建物は京都・奈良にもありません、ここでしか見れない珍しい建物いかがでしょうか。
笠森寺は観音霊場です「笠森観音」と呼ばれている場所です。最近ここの「黒い招き猫」が人気だとか、何もかも珍しいところなのです。

笠森観音
黒い招き猫
今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
爽やかな朝!!秋晴れの空10月の始まりにふさわしい天気となりました。どこかに出かけたくなりますねぇ~
では、本題と参りましょうか、千葉県編をスタートしてまず第1弾が超有名どころ成田山新勝寺でした。では次はどこか・・・・
千葉県にはまだ、どうしても外せない建物があります。それが長南町にあります。房総半島のほぼ中心、市原市の先にある山の中にある「笠森寺観音堂」になります。まずは姿をご覧ください。

笠森寺観音堂
このお堂は国指定重要文化財建造物の中で唯一の「四方懸造り」の建物なのです。「懸造り」で有名な建物は京都・清水寺になりまが、清水寺は一面だけになりますが、この笠森寺観音堂はすべての面・4方が「懸造り」なのです。山の頂に建っている、他にはないこのお堂、面白いと思いませんか。その先の話は次回ということで。
これから午前中だけですが打合せがありますので出かけます。今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
九月最後の日曜日になります。涼しい朝、曇り空今日は晴れるのでしょうか・・・もう暑い日は来ないのか・・・例年だとそうなのですが、最近はわかりませんねぇ~
今日も本題と参ります。成田山新勝寺の話をしていましたがその最終回。前回本堂の変遷、現在も賑わっている成田山江戸時代に大ブレークして本堂を大きくしていきました。そして昭和になって今の本堂となった流れ。皆さんご存知でしょうが、現本堂の写真掲示します。

成田山新勝寺本堂
成田山は他に2棟の国指定重要文化財建造物があります。仁王門:江戸末期・文政13年(1830)建立、もう一つは額堂:江戸末期・文久元年頃(1861頃)建立、この二つのになります。江戸時代の庶民の信仰心を感じることのできる建物です。参詣者が奉納した額をじっくり見るのも楽しいですよ。

成田山新勝寺仁王門

成田山新勝寺額堂
簡単ですが・・・今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
台風来ています・・・この連休は雨の中、秋の行楽は持ち越しと言ったところでしょうか・・・何事もなく台風が過ぎてくれるのを祈りながの連休となりそうです。今日も涼しいので体調管理お気を付けを・・・私は木曜に風邪をひき金曜日は熱が下らなかったので休みをもらった次第・・・皆様もお気を付けください。
今朝は時間がありますので、本題と参りましょう。
成田山新勝寺の話をしています、前回まで三重塔の話でしたが、今日は他の国指定重要文化財建造物を紹介します。
前もここで話をしましたが、新勝寺には5棟の国指定重要文化財建造物あります。今日は光明堂と釈迦堂を紹介します。

成田山新勝寺光明堂

成田山新勝寺釈迦堂
これが両方のお堂の姿です。光明堂は江戸中期・元禄14年(1701)建立、釈迦堂は江戸時代末期・安政4年(1857)建立のお堂です。この二つのお堂は元々は本堂として建てられて使われていたお堂なのです。そして、昭和43年建立の建築家:吉田 五十八(よしだいそや)設計による本堂がいまの本堂となります。
江戸時代に大ブレークして現在まで流行っているお寺「成田山新勝寺」そのお寺の歴史をお堂の変遷でも感じることができるかと思います。このような見方も面白いかと思います。
ということで今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。