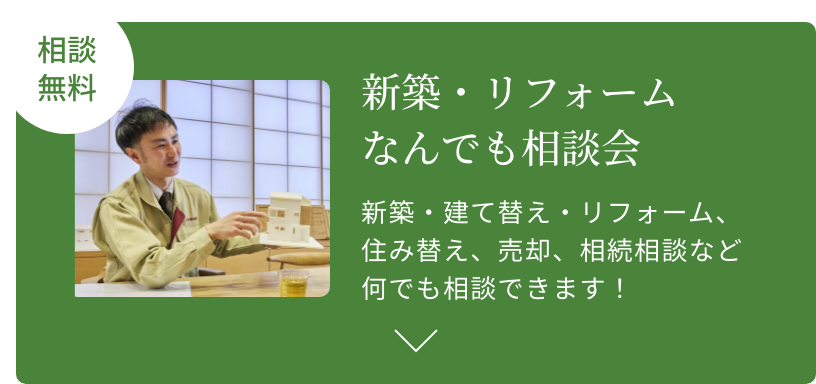日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
気持ちの良い晴れの朝!もう秋晴れ!気持ちの良い日曜日の始まり~となりました。どこか行きたくなる気持ちになりますね。
今日は時間があるので本題と参りましょう。先週は夕方の「日曜の朝に」となった簡単なものでしたが、先々週から始まった千葉県編の成田山新勝寺の続きのお話・・・
どうですか、新勝寺三重塔!豪華絢爛これでもかとテンコ盛りの彫刻群、すごいですよね~。
江戸時代の社寺建築は、建物の様式・工法は前の時代で出尽くしてしまい、新しい様式が生まれなかったこと、あと、社寺建築の規格化が成立してしまい進化が生まれ難くなったことのより、建築の装飾技術:彫刻・錺金物(かざりかなもの)の発達が顕著になりました。その一つがこの三重塔と言えると・・・・
シンプルイズベストとよく言われますが、同じ日本の建築物・歴史の流れの一部である江戸時代の装飾建築、あまり好みでないと思っている方も、改めて見てはいかがでしょうか?なぜこれを造ったのか?などの歴史的背景と一緒に考えてみると見方も変わってきます。
今日は新しい建物を紹介するのが、三重塔の話の続きになってしまいました。その話は次回にいたしましょう。
ということで、今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
とは言え実は今は夕方過ぎ、宵の口となってしまいました。朝ではないのです・・・
言い訳です・・・今日は成田東弊社モデルハウスの内覧会のために休みでは、なかったので・・・今家に帰って来たところです・・・・
実はその途中に、今日は日曜日だと気付いたわけで・・・これから夜の日曜日を楽しみます(ビール飲むだけですが・・・)
ということで、今日はこの辺で失礼いたします。残りの日曜日良いことがありますように・・・
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
また日曜日やってきました。今朝はいつもより涼しい、曇り空なので強い日差しもありません。
今日は過ごしやすそうな日曜日になるのでしょうか・・・
さて、いよいよ本題と参りましょう。
千葉県の一番手は、皆様ご存知の「成田山新勝寺」をまず取り上げます。この新勝寺お参りに行った方は多いかと思います。
広い境内数ある建物の中で国指定重要文化財建造物は5棟あります。
その中でまず初めに紹介するのは三重塔です。こちらがその写真!

成田山新勝寺三重塔の見上げ
江戸時代中期正徳2年(1712)建立の三重塔なのですが、何しろ装飾がすごい!!!
なかなかここまで装飾密度の濃い塔は見ることができません、軒天井が一面の彫刻となっていて、良いか悪いかは置いといて、これだけ徹底して装飾を施した力には驚くばかり・・・
本堂の前にあるのでお参りに来た方は目にしているかと思いますが見いて飽きない建物の一つと言えます。
見たこともある方も是非もう一度じっくり見てみてはいかがでしょうか

成田山新勝寺三重塔軒天井
今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
晴れませんねぇ~しかも蒸し暑い、何となく体が重いです。そうなると気分も重くなります・・・・
いよいよ本題の古建築の話・・・千葉県編の話スタートしましょう。
調べますと千葉県の国指定重要文化財建造物は29件あります。この29件の中には複数の棟が指定されているところもあるので、棟数でいうともう少し多い件数になります。
この中に国宝指定の建造物はありません。しかしバラエティーに富んだ建物が揃っていますので、これよりその建物たちを巡っていきましょう。
とは言うものの、本題に行く元気がないもので、今日は前ふりだけになってしまいましたが・・・というわけで次回より紹介していきます(仕事がなければ)
この辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
「日曜の朝に」とは言うものの、今朝は火曜日です、8/11より、夏季休暇(8/15まで)、その最中の日曜日ということで、家族を連れて出ていました。ということで、今日になってしまいました。遅ればせの「日曜の朝に」、ご容赦ください。
今日は、その出かけた中での話を・・・八ヶ岳や霧ケ峰辺りの高原を巡った来たのですがその途中で、自分が見たかったので(家族は興味がなっかたのですが・・・)寄ってみた所の話を・・・
そこは茅野市尖石(とがりいし)縄文考古館という資料館。そこにある2体の国宝土偶を是非直接見たかったので・・・・こちらがこの写真です。

縄文のビーナス
こちらが「縄文のビーナス」と呼ばれるいる土偶。

仮面の女神
もうひとつが「仮面の女神」と呼ばれている土偶です。
縄文のビーナスは昭和61年に出土・平成7年に国宝指定となっています。もうひとつの「仮面の女神」は平成12年に出土・平成26年に国宝指定となっています。
八ヶ岳山麓は5000年前縄文文化が花開いていたところで大小300以上の遺跡があるとのこと、その遺跡の出土品が展示されている資料館なのです。その中でもこの2体の土偶は、素晴らしい!、写真では見ていましたが実際に前後左右上から見ると今まで感じなかった造形力・模様のデザイン力はすごいと感じることができ、久々に鳥肌が立ちました。この距離で実物が見ることができるのはここならでは!これが国立博物館にきたらゆっくりと見れないかと・・・やはり現地ならではと・・・ただし、たまに出張しているそうですのでご注意を・・・
今日はこの辺で失礼いたします。明日から仕事です。きょうはゆっくりとすごします。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
蒸しますねぇ~汗かくだけで蒸発しないので熱がこもります。皮膚呼吸ができなくなる~
といった具合。はっきりしない曇り空、天気はどうなるのでしょうか・・・
今日も成田東の弊社モデルハウスの内覧会あります。案内担当になっていますので、これから出かけます。
まずは会社に・・・内覧会は10時から16時まで開催しています。ご予約は不要ですお気軽にどうぞ。
昨日は暑い中、お越しいただきありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
そうです!昨日のお客様にもいらっしゃいましたが、今「阿佐ヶ谷の七夕祭り」開催されています。
その足でこちらにも・・・というのは以下かがでしょうか。
ということで、今日も簡単なブログとなってしまいますが、ご容赦ください。
この辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
曇り空、少し雨が頬にあたるような当たらないような・・・日差しがない分少しは涼しい感じがします。湿気はありますが・・・・
これから仕事の日曜日になりますので・・・簡単にさせていただきます。
今日は内覧会があり、担当になっているのでこれから出かけます。
本題の古建築の話も新しい展開になります。またたまには違った話も良いかなぁ~とも・・・・
ということで、簡単ですが今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。(本当に簡単で申し訳ありません。)
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
曇り空の日曜日・・・今日はこの様な天気なのでしょうか・・・
昨日はお客様感謝デーを行いました。暑い中お越しいただきましてありがとうございます。本当に暑かったです・・・今日はちょっとバテ気味なのでゆっくりと過ごすとしましょう。
時間のあるのでいつもの本題と参りましょう。
いよいよ今回にて埼玉県編は終わりとなります。たぶん・・・
紹介する建物は川島町にあります「広徳寺大御堂(こうとくじおおみどう)」となります。大御堂といっても3間×3間の前回紹介した福徳寺阿弥陀堂に似たこじんまりとしたお堂です。この大御堂時代は福徳寺阿弥陀堂の鎌倉時代よりは新しく室町時代後期(1467~1572)150年くらい新しい建物になります。茅葺屋根の素朴な関東地方らしいお堂です。

広徳寺大御堂
写真を見てわかる通り(わかる方はわかるのですが、わからなくても気にしないでください)このお堂は鎌倉時代にできた建築様式の禅宗様の意匠が所々に見られます。良く分かるのが扉の形かと、「桟唐戸」という扉で禅宗様の特徴のひとつです、前回の福徳寺阿弥陀堂は蔀戸(しとみど)という格子の扉で和様の意匠になります。このように様式を知りながら古建築を見るのも楽しいものなのですが、ここまで詳しくなることもないのかなとも・・・知りたい方はいつでもお答え致します。
次回からは千葉県に移っての古建築巡りを・・・あっ神奈川県まだでしたね、どちらにしましょうか・・・
ということで、今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
毎日暑い日が続いています。体調はいかがでしょうか?海の日も明日となりいよいよ名実ともに夏がやってきます・・・・ということは梅雨明けということも・・・天候バランスよくいきませんね・・・過ぎたるは猶及ばざるが如し・・・というところでしょうか。

福徳寺阿弥陀堂
先週のブログでお話しした、埼玉県飯能市にある、埼玉県最古の建造物「福徳寺阿弥陀堂」の写真になります。
先週はなぜか写真を載せることができなかったのですが、今日はできましたので、遅ればせながら・・・銅板葺き屋根なのですが茅葺屋根の形にしているので屋根のボリュームが強い形になっています。間口と奥行が同じ長さなので屋根は上から見ると正方形をした「方形(ほうぎょう)屋根」となります。よく阿弥陀堂と呼ばれる建物はこのような3間×3間の正方形をした建物がいくつかあります。有名な国宝建造物である岩手県平泉の中尊寺金色堂もこのような阿弥陀堂の代表的な建物となります。
と言っているうちに、結構字数が稼げたようです。久しぶりの連休なので、これから子供を連れて出かけ無くてはならない・・・ようです。
今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
言いたくはないですが・・・暑いですねぇ~今日も30℃超えになるのでしょうか。
それでも弊社設計施工のきれいな空気のゼロエネの住まい=モデルハウスの内覧会開催しています。
お時間ありましたらぜひお越しください。10時から16時までやっています場所は杉並区成田東ですこのホームページのイベント情報をご覧ください。
今日は2週にわたり怠けていました本題の古建築の話に参ります。
埼玉県編の途中でした・・・もうそろそろ埼玉県も終わりに近づいていますが、今日は「福徳寺阿弥陀堂」を案内いたします。
このお堂、3間×3間の小さなお堂なのですが、埼玉県で一番古い建築物なのです。
場所は飯能市西武秩父線と並走している国道299号線沿い、駅では東吾野になります。
山のふもとにひっそりと佇んでいます。県内最古の建物ですが決して有名でもなく、観光地にもなっていません昔からのそのままにあるといった、とても感じの良い雰囲気の中に立っています。
このお堂、様式から言いますと「和様」。鎌倉時代に大陸からやってきた様式が入っていない、優しい感じの建物になっています。
当時の住宅の雰囲気を持っている、知る人が見ればなかなか良い建物なのです。
こちらは何かのついでに、というところではないので、見たいと思わないと行かないところかと・・・
※写真を載せたいのですが・・・うまくいきません。ごめんなさい。
ということで、この辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。