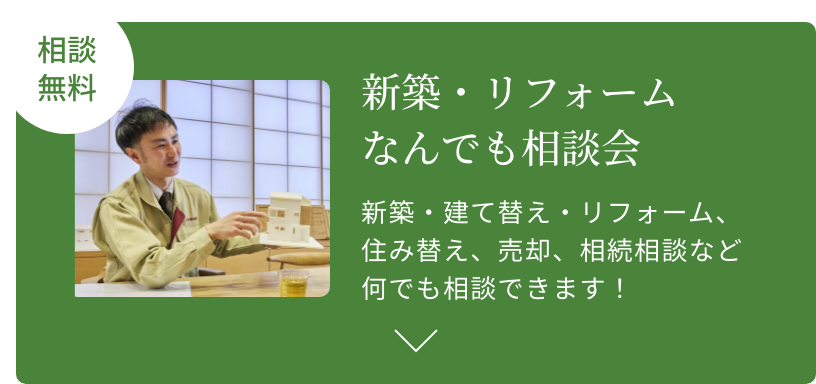日曜の朝に
おはようございます。設計担当高橋です。
といっても、後出しの「日曜の朝に」・・・この日曜はホームオーナー様ご案内ツアーがあり、また打合せ準備も目白押し朝早くの出勤・・・すっかり日曜であること・・・忘れておりました。
と言うことでいいわけでした。失礼します。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
涼しい日が続いています。日曜の今朝も爽やかな涼しさ・・・寝るのに心地良い・・・この涼しさで暑さに耐えてきた、この身体から何か気だるさが出てきている感が・・・重い・・・
この涼しさ今日あたりまででしょうか・・・また暑くなると天気予報では言っています。そうなっても、またに身体にきついですね。
今年は何となく蝉が多いような気がします。道に落ちて死んでいる蝉がいつになく多いような・・・東京でもクマゼミの声が年々増えてくる気もします。もう8月後半になり子供たちの夏休みも少なくなり・・・自由研究というものやらないと・・・うちの子もそわそわと・・・自分が子供のころはその時のBGMはツクツクボウシ・・・まだそんなに鳴いていませんが、夏の終わりを告げるツクツクボウシもうそろそろでしょうか・・・
ツクツクボウシの声を聞くと心が忙しくなるのは私だけでしょうか・・・
ということで、今日はこの辺で失礼します。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
今日は土曜日の朝です。そして休日初めての「山の日」。そして夏季休暇初日ともなります。明日が日曜日になるわけですが・・・明日の朝はブログができる状況ではなさそうなので、前日前倒しとさせていただきます。
台風が過ぎ、また以前と同じ暑さが戻ってきました・・・困ったもので・・・冷房で体調を崩された方も多いのでは・・・電車でもいつになくマスクの方多いような・・・
今日は時間があるので、先々週の続きということで、建築の話を・・・
三渓園臨春閣の話をしています。数寄屋風書院造りのお殿様の別荘として建てられた建物、別荘なので日常とは違うものを求め、形を崩した数寄屋風にしたのだと思います。
この「崩す」ということ→建築で「真・行・草」と言われています。
元来、書道の真書(楷書)、それを崩した行書、さらに崩した草書の3書体のことですが、建築にも用いられます。
ただし3つの境目は明確ではなく、こんな感じ~で区別しているようなのですが・・・
簡単に言うと書院建築=真、数寄屋風書院建築=行、茶室=草というところでしょうか、簡単ではないかも・・・まぁ、そのような目で建築を見るのも様でしょう。
「数寄屋」ある意味、何でもありの建築、ただしそこにはセンスが見えてくる、美しいかそうでないかが問われるもの・・・本来はお金をかけずにそのあたりにある材料で草庵を造るということが・・・いつの日かお金持ちの建物のような扱いになっていた・・・そんな建築とも言えます。
ということで、今日はこの辺で失礼します。よい土曜日・祭日・日曜日・夏季休暇をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
相変わらずの暑い朝、今日は現場見学会の担当となっておりますので、もう出かけなくては・・・
来週はもう夏季休暇となるのか・・・それを楽しみに今日も暑さと勝負です・・・もちろん見学会に来たお客様が暑い中お越し下さることに感謝、来てよかったなと思っていただけるような、案内を・・・そのような思いで、行って来ます。
ということで今日は(も?)簡単にさせていただきます。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
東京は台風が去り蒸し暑い空気が朝から迎えてくれています。皮膚呼吸ができない感じ・・・蝉が元気に鳴いています・・・
今台風は関西を過ぎ西へ・・・先日の豪雨災害のエリアへ・・・何事もなく過ぎ去っていただきたいのですが・・・昨日は弊社の感謝デーも中止となり、台風の影響を受けてしまったということで・・・
あっ、今日は休みです。本当に久しぶりですが本題の建築の話、ひとつ参りましょうか・・・
神奈川県横浜市にある三渓園の建物巡っている途中でした、その中でもう一つ触れたい国指定重要文化財建造物は「臨春閣」。
この前は「聴秋閣」今度は「臨春閣」どちらもなかなか、ネーミングが良い!
まずは臨春閣の姿を

三渓園臨春閣
こちら江戸時代初期の数寄屋風書院造の建物になります。
慶安2年(1649年)紀州徳川家の別邸と考えられています。豊臣秀吉の聚楽第の遺構ともいわれていたことも・・・
この建物はその後取り壊しと移築を幾度か繰り返し、大正6年にこの地に移築完了、今に至っています。
この建物別荘です。すごいですよねぇ~、まあ、紀州徳川家ですから全国ナンバー3に入る大名のお殿様の別荘となるわけで、当然といえば当然か。
本邸=城内にある御殿、こちらはパブリックな建物ですから格式ばった書院建築。別荘はそれよりプライベートな建物ということで数寄屋造りになるようです。
この臨春閣、武家による数寄屋風書院となります。公家による数寄屋風書院建築「桂離宮」と比べるのも面白いかと・・・今回は数寄屋建築なるもの触れてみたいと思います。まずは今日はその建物紹介ということで・・・
それでは失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
我が家のパソコンがことのほか早く修理から戻ってきました。
ということで日曜の朝に「日曜の朝に」をお送りすることが出来るようになりました。(皆様にはどうでも良いことでしょうが・・・)
それにしても暑い・・・朝のさわやかさが全然ない、朝のラジオ体操で熱中症になってしまうのかのようです。(夏休みになったので公園のラジオ体操のにぎやかです)
その熱い猛暑のさ中ですが、本日は内覧会がございます。今日はそちらに参りますのでこれから出かけます・・・仕事です・・・暑いです・・・言いたくはないですが言ってしまいます・・・暑いです。
本題はパソコンが戻ってきてなどと、先週言っておりましたが・・・仕事なのでお許しください。
皆様、暑さにはくれぐれもご注意ください。そしてよい日曜日をお過ごしください。失礼いたします。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
あっ!まだ日曜日ではありませんね、土曜日の夜なのです。
先週の日曜の朝でも触れましたが、ただいま自宅のPCが入院中で、明日に発信できないので半日早いですが、今とさせていただきます・・・・
それにしても暑いです・・・明日の日曜日も・・・
今東京都内はお盆です。まるで8月のお盆の時のようです。
お盆・・・私の家にはまだ仏様はいないのでしませんが、祖父祖母ご位牌のある本家ではお盆の行事をしていました。(過去形は自分のこと、本家では当然、今もしています。)
子供の頃は7/13に迎え火を提灯にともし、2方向に別れそれぞれの場所からご先祖の霊をお連れしていました。(どうも先祖が2箇所のお寺にいるそうでそうなったようです。)
今考えるとなかなか風情のある行事だったなぁ~と・・・浴衣に着替え、もうすぐで夏休みのわくわく感、その帰りにはスイカ1玉もらうのが毎年楽しみだったことなど懐かしい・・・
季節感のある行事いいものですね、季節の行事、自分の子供にはあまり体験させていないので、いけないなと思う次第です。
と次数もそこそこになりましたので、今日はこの辺で失礼いたします。
本題はPCが治って帰ってきたときとしましょう・・・良い日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
朝から暑い!!今事務所のPCよりお届けします。と言うのは自宅のPCが壊れたようで入力できず、今日は内覧会があるのでまず事務所に・・・・
と言うことなので、もう出かけます、本当に今日は短いナイヨウで申し訳ございません。
では早々と失礼いたします。良い日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
今日も朝から暑い~さわやかさがなぁ~い、きつい日差しが体を・・・
今日は仕事です・・・これから出かけます。
本題は次回とさせていただきます。(来週も見学会では?・・・)
と言うことで、今日は本当に短くさせていただきます。簡単で申し訳ございません。
よい日曜日をお過ごしください。
日曜の朝に
おはようございます。設計担当の高橋です。
涼しい朝の日曜日、昨日の雨でしっとりとした空気感、朝は心地よいのですが・・・昼間になると湿気に変わり不快なものに・・・今は曇天、梅雨らしいといえばそうなのですが、今日はどのような天気になるのでしょうか・・・昨晩の帰りは月が見えていたのですが・・・
さて、本題に参りましょう。先週の続きということで、まずはこちらの写真を

三渓園聴秋閣 正面
この三渓園聴秋閣の話の途中でした。屋根も複雑、平面構成も複雑な建物でどのアングルから見ても表情の違う建物です。移築建築物なので現在のロケーションは建物に合わせ周辺が作られていますが、元々京都二条城内の建築物、たぶん庭園内の建築としてそこに合わせて建築されたからこそ、この形になったのかと・・・元の姿を見てみたいと思てしまいます。それがこの形の理由なのかと・・・
とにかく良い建物です。何度見ても飽きない建物、また周りも四季それぞれ変わりますのでその楽しさもあります。この建物はお薦めです。(有名だからご存知でしたか・・・)
ということで、今日はこの辺で失礼いたします。よい日曜日をお過ごしください。